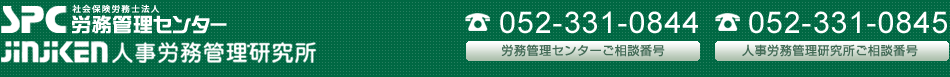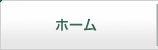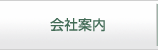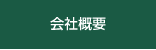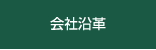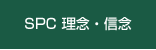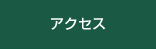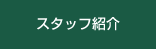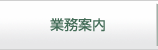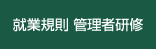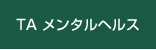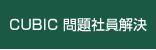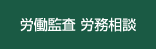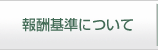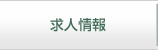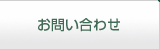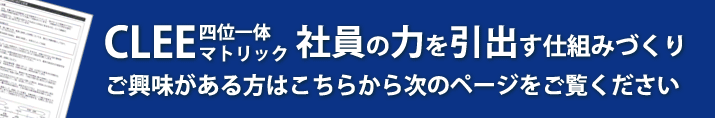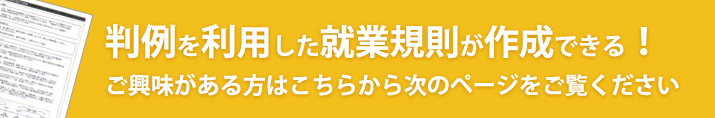セクハラ事実確認で会社協力、使用者に責任は
2026/01/09
ジャパンチキンフードサービス事件【東京地判 令和6年10月22日】
【事案の概要】
都内で複数の飲食店を経営している会社(Y社)に勤務していた女性(X)が、勤務先で性的な嫌がらせを受け、精神的苦痛を被ったとして、Y社に対して使用者責任または安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき、慰謝料300万円および遅延損害金の支払いを求めた。
Xは、令和4年11月に店舗での勤務を終え、帰宅しようとしたところ、同店の外国人スタッフより上着の袖を引っ張り自身の方へ引き寄せたり、服の上から下着(ブラジャー)を外したことが認められる。
その後、Xは令和5年4月頃に「ご連絡」と題する書面をY社に送付し、上記の嫌がらせを受けた旨と損害賠償を請求した。
【判決のポイント】
- 性的な嫌がらせの有無について
身体を引き寄せたり、下着を外した事実は認められる。
Xは当該店舗で勤務するようになってからまだ3日程しか経っておらず、行為者による身体的な接触等を許容することは考え難い。
当該行為は店舗内で行われたこともあり、Y社は使用者責任を負い、慰謝料30万円と認定する。
- Y社の安全配慮義務違反について
Y社は職場でのセクハラを容認しない方針を従業員へ認知させ、苦情や相談窓口を設置し、安全配慮義務違反はないと主張するが、このような対策が講じられていたことを認めるに足りる証拠はない。
また、Y社はXの相談に応じ、録音データを渡したり、店舗を変更したりするなど対応を取っているが、Xや行為者から詳細な聞き取りを行ったり、Xに謝罪をするなどの対応はしておらず、セクハラ等の訴えがあった会社としての対応としては不十分である。
慰謝料の請求を受けた際にも、その話し合いに応じることなく、むしろ訴えを提起するとシフトを減らすなどの行為に及んでおり、その慰謝料は30万円と認知する。
【SPCの見解】
職場でのセクハラに関しては、男女雇用機会均等法に定められており、セクハラに対する方針の明確化や相談窓口の設置、事後の迅速かつ適切な対応をするなどの雇用管理上の措置が求められています。
一方、パワハラについては、労働施策総合推進法によって、同様の事業主の講ずる措置が定められています。
本件の事案についても、会社側の録音データの提供や希望に沿った店舗の異動だけでは、不十分とされました。
慰謝料の60万円だけでなく、企業のイメージダウンにも繋がるため、ハラスメントに関する相談や訴えがあった場合は事実関係を迅速かつ正確に把握し、当事者からのヒアリングを徹底して被害者と行為者に適切な措置を行うことの重要性を教えてくれる判例でした。