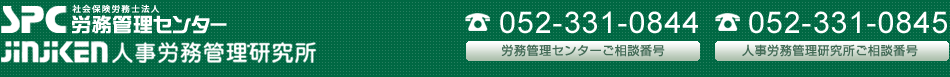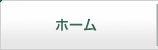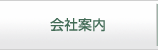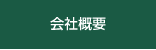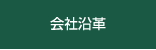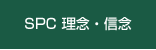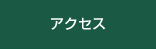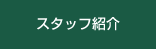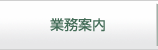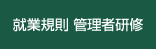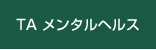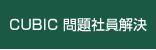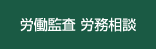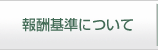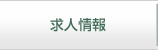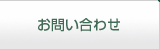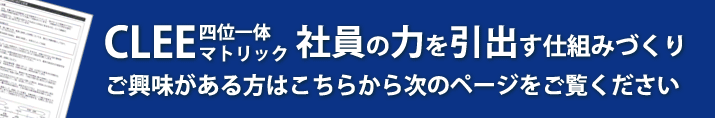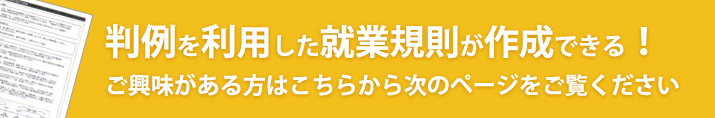60年以上も続いた錬成費の支給取止めは有効か
2026/01/09
中日新聞社(錬成費不支給)事件【東京高判 令和6年3月13日】
【事案の概要】
Y社では、昭和30年代から60年以上にわたり毎年「錬成費」を支給していたが、就業規則や賃金規程、労働契約等のいずれにも錬成費の記載はなかった。
支給時期や金額に変動はあったものの、昭和50年には毎年1回(3月)に3,000円を支給するようになり、平成21年までは現金・手渡しをしており、平成22年以降は給与支給とあわせて振込による方法になり、課税所得として扱われるようになった。
令和2年1月、Y社は2つある労働組合に対し、錬成費を不支給とする旨告知し、同年より支給しなくなった。
Y社の従業員達(X)は、錬成費の支給は労使慣行または黙示の合意があると主張し、錬成費の支給を求めた。原審(東京地判 令和5年8
【判決のポイント】
- 労使慣行の成立要件
民法92条(任意規定と異なる慣習)において、①長期間にわたって反復継続して行われ、②労使双方がこれを明示的に排除しておらず、③当該慣行が労使双方(特に使用者側は当該労働条件について決定権または裁量権を有する者)の規範意識によって支えられている場合であることが必要だとされています。
- 労使慣行の成否
本件において、①と②は認められるが、③は認められない。錬成費の支給は給与とは異なる扱いをしており、春闘交渉においても、労使間で協議された形跡はない。支給方法等の変遷をみても、交渉や経緯が行われた形跡はなく、Y社が一方的に決めてきた経緯に照らせば、労使双方の規範意識に基づく労使慣行とは認められない。
- 黙示の合意の成否
錬成費の支給はY社の任意的恩恵的なものとみるのが相当であり、労使間で協議された形跡等がない以上、明示的な合意と同等の効果が付与される黙示の合意が存するとは認められない。
【SPCの見解】
本件のように長年、支給していた金員や制度などを突然、廃止したり変更したりする場合に今までの「労使慣行」として取扱いに悩む場合があります。
労使慣行となるためには、単に長年の慣行(一定の範囲において長期間反復継続して行われていた)だけに重点が行きがちですが、②労使双方がこれを明示的に排除しておらず、③当該慣行が労使双方(特に使用者側は当該労働条件について決定権または裁量権を有する者)の規範意識によって支えられていることも必要にもなります。
不利益変更の問題も出てくる可能性もあるため、支給や制度の趣旨、できた経緯など含めて把握と検討しておく重要となります。