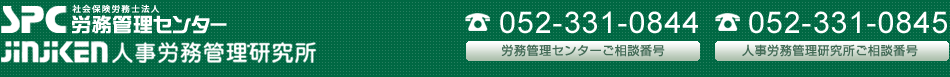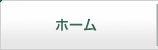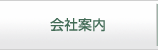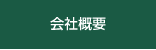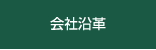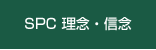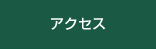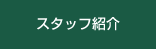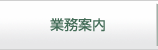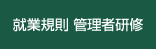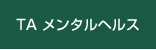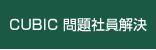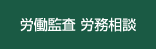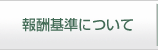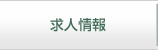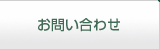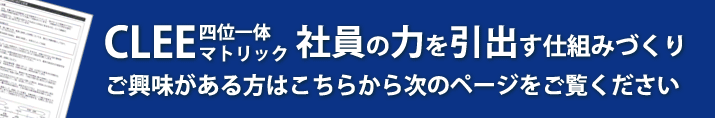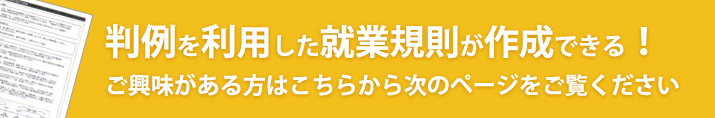上司へのメール内容はハラスメントで減給処分
2026/01/09
明和住販流通センター事件【東京地判 令和6年3月21日】
【事案の概要】
Y社は不動産販売を目的とする株式会社である。Xは、平成17年10月頃にY社へ正社員として入社し、腎臓疾患を患って以降は、短時間勤務として就労していた者である。Xは、令和3年4月5日頃、上司であるA次長に「ストレスを感じ、気持ち悪い」や「頼りにならないにも程がある」とするメールを送信したことにより、令和4年8月に降格処分を受けた。降格により、基本給は2万円の減給となった。
その後、同年9月27日、Y社から同日付で普通解雇する旨の通知を受けた。解雇通知書には、Xの言動がXの言動が他の従業員および上司の人格を著しく傷つけ、注意されても反省の態度を示さず、同様の言動が繰り返されていること。その他、メールおよびパソコンの私的目的で利用するなど業務の懈怠が著しい旨記載されていた。
Xは、Y社の行った降格処分、解雇処分、賃金の減額は違法として、訴訟を提起した。
(賃金減額処分については、割愛します)
【判決のポイント】
(1)降格処分の有効性
降格処分の原因となった上司へのメールについては、上司に対するハラスメントであり、企業秩序を乱す行為である。行為の内容、程度に照らせば、当該降格処分が重いとは言えず、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効に該当しない。(降格処分は有効である)
また、メール送信より約1年4ヶ月後に降格処分を行っているが、Y社がそのメールを知ったと推認でき、長期間放置したとは言えない。
(2)解雇処分の有効性
XはY社の代表取締役へも社内の一斉送信のメールを用いてハラスメントをしていた旨主張する。しかし、内容は社内の労務管理に関するものであり、直ちに不相当とまでは言えない。
パソコン等の私的利用も、Y社の私的利用の主張は推測レベルであり、真に業務と関係ない内容であるか否かも判然としない。
また、Y社が注意指導したと認めるに足りる客観的な証拠もなく、Xの言動は一部不適切なものが認められるものの、改善の余地がなかったとまでは言えないから、上記のパソコン等の私的利用を理由とする解雇は認められない。
【SPCの見解】
降格処分は認められた一方で、パソコン等の私的利用を理由とする解雇は無効と判断されました。
判決のポイントにもあるとおり、「Y社が注意指導したと認めるに足りる客観的な証拠もなく・・・」と判断されており、Y社としてはしっかりと注意指導を行い、改善を促していれば異なった判断になっていた可能性も感じました。
企業側はもしものために、注意指導書の交付や面談など行い、継続的な対応と客観的な証拠を残すことの重要性を教えてくれる判例でした。