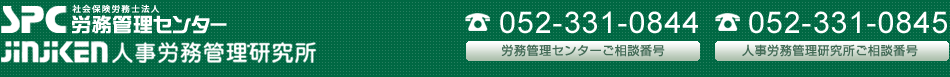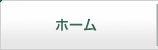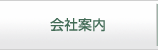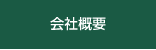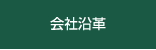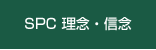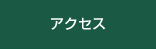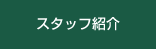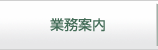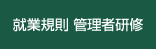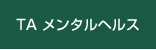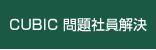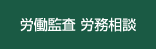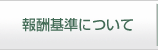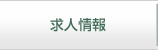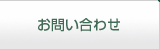障害者の労務管理について
先日以下のようなニュースを見ました。
東京都の区から清掃作業を受託していた団体連合会が都の最低賃金の半額程度で知的障害などのある清掃員を従事させていたことを関係者が告発をし、新宿労働基準監督署がこれを受理したとのこと。同会や区は、清掃は労働ではなく一般就業が難しい障害者への訓練だったと主張しているようです。
最低賃金法は原則障害の有無にかかわらず、すべての労働者に等しく適用されます。「障害があるから」「簡単な作業を任せるから」といった理由で、企業が一方的に最低賃金を下回る給与を設定することは、明確な法律違反となります。
ですが現実には重度の知的障害を持たれる方を労働者として雇用した場合、指揮命令を理解することが困難なこともあり、現場において目を離すことができないといったこともあるようです。
障害者を雇用する場合の会社が押さえておきたい制度についてです。
○最低賃金の減額の特例許可制度(最低賃金法第7条)
この制度は、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者等以下の対象者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に最低賃金の減額を認めるというものです。
「対象労働者の範囲」
① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
② 試の使用期間中の者
③ 基礎的な技能および知識を習得させるための職業訓練を受ける者
④ 軽易な業務に従事する者 その他厚生労働省令で定めるもの
○障害者雇用促進法における障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度
この法律により企業に対して、雇用する労働者の2.5%に相当する障害者を雇用することを義務付けています。雇用率は定期的に見直されR8年度に2.7%に上がる見込みです。
労働者の人数要件がありますが、これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています。
○障害者雇用促進法(平成28年4月施行)による障害者労働者への合理的配慮
この法律により職場で働く障害者に対する差別禁止(賃金を引き下げる、昇給をさせない、食堂や休憩室の利用を認めない等)や合理的配慮の提供(車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整する等)が義務付けられています。合理的配慮の提供については当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除きます。
先のニュースのようなことが起きては会社の信用を著しく損なうことになります。制度や法律を知り、適切に障害者の労務管理を進めていきましょう。障害者雇用についてもお悩みがあればご相談ください。