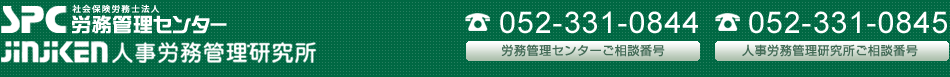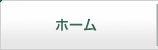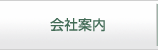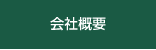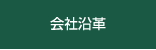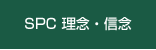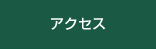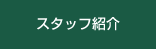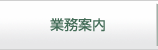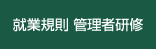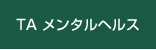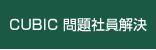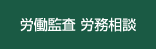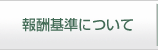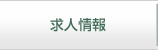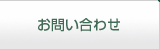増える静かな退職
「静かな退職(quiet quitting)」という言葉に考えさせられています。
「静かな退職」とは、アメリカのキャリアコーチにより提唱されたもので、本当に退職するわけではなく、仕事に対する熱意を失い、退職しているような気持ちで出世や昇進を望まず、必要最低限の仕事をしながら在職し続けることです。
主にはZ世代の若者を中心に浸透しているようですが、若者ばかりとは限りません。要因として、①ハッスルカルチャー(*1)の衰退、②ワークライフバランスの重視、③キャリアパスの不透明化があるとのことです。
*1ハッスルカルチャー:仕事を人生の最重要項目と位置付け、多忙であることや生産性の高いことを美徳とする考え
博報堂生活総合研究所は以下のような調査結果を発表しています。
【定点調査1992-2024博報堂生活総合研究所】
(2024年 調査対象20~69歳男女 2,510人 首都圏+阪神圏)
・基本的に仕事が好き:46.2% ・会社に対して忠誠心がある:25.0%
・会社の中で出世したい:13.9% ・同じ会社で仕事を続けたい:44.7%
・「気楽な地位」or「責任ある地位」で気楽な地位の選択:83.8%
https://seikatsusoken.jp/teiten/category/9.html
SNSの普及により自分を表現できる場所が増えると自己実現を仕事に求める若者も減っているように感じます。静かな退職という価値観を否定するものではありませんが、会社の組織力に影響はありそうです。
先に記載した要因3つの中で、ハッスルカルチャーやワークライフバランスは個人ごとに価値観や環境が異なり擦り合わせることは困難です。会社が採れる効果的な対策は社内のキャリアパスを明瞭にしてモチベーションに働きかけることでしょう。
静かな退職を防ぐための企業側の対策
・従業員エンゲージメント(会社に対する信頼や帰属意識)を調査する
従業員エンゲージメントを調査することは、組織の健康度を把握するために不可欠です。エンゲージメントが高い従業員は、仕事に対するモチベーションが高く、業績に良い影響を与えます。
・人事評価制度を見直す
公正で透明性の高い人事評価制度を導入することで、従業員のモチベーションを高めることができます。成果だけでなくプロセスや努力にも評価することも重要です。上司だけでなく同僚や部下から多角的な評価を取り入れることも公正さが担保されます。
・キャリア支援制度を充実
会社にいることで自分自身にも財産となるスキルアッププランを策定します。具体的には会社のおける職務と役割を明瞭にすることや資格取得支援を構築します。
静かな退職を防ぐためには、企業側が対策を講じることが重要です。公平性の高い評価制度や前職までのキャリアを考慮しつつ、役割を明確した役割等級による賃金制度の設計を推奨しております。ぜひご相談ください。