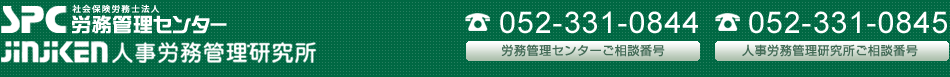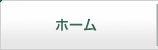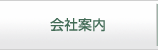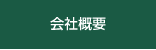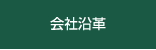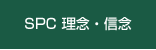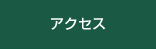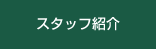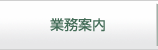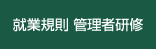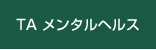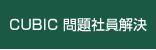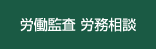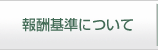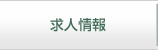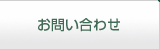令和7年10月1日 育児介護休業法改正に向けて
先日の朝刊に「出生数 初の70万人割れ…」と出ていましたね。政府の予想よりも15年早く出生数が減少しているという驚きの内容でした。少子化ということは、将来の労働力人口の減少にも繋がり、今の社会保障制度の仕組みでは、高齢者を支える若者が必然的に減るので、制度の維持が困難となることが予想されます。他人事ではありませんね。
少子化で問題となるのは社会保障制度だけではないので、子どもを生み育てようと思ってもらうにはどうすればいいのか…各省庁でいろいろな議論が繰り広げられていることが想像できます。
雇用保険の4月の改正では、働きながら子どもを生み育てる経済的な支援の面から、育児休業中の給与の代わりとなる給付金が手厚くなりました。男性の育児参加はここ数年、方々で力を入れていることが分かりますが、夫婦ともに育児休業を取得した場合に上乗せされる給付金の新設です。また、育児休業後に短時間勤務制度を利用する2歳までの子を養育する人にも、新たな給付金制度が始まりました。
そして、育児介護休業法の10月の改正は、子育てをしながら働く際の“柔軟な働き方”の措置の導入を、すべての事業主に求める内容です。対象となるのは、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員です。
「選択して講ずべき措置」として厚生労働省が次の①~⑤を挙げ、この中から2つ以上を選択して制度化することを事業主に義務付けています。
① 始業時刻等の変更※所定労働時間は変更しない
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
⑤の短時間勤務制度は、既に3歳未満の子は対象となっているため、こちらを選択する事業主も多いことと思います。ただし、今回の改正のポイントは、どの措置を導入するかを選択する際に、過半数労働組合または労働者代表からの意見聴取の機会を設ける必要がある点です。
事業主が勝手に導入した制度が、結局労働者にとっては利用しづらい制度では意味がありません。労働者代表の意見も交えて選択導入した2つの制度のうちから、対象労働者はいずれか1つの制度を選択して利用するという仕組みです。
5つの内容のうち、まず➂保育施設の設置運営等は多くの企業は選択しないのではないでしょうか。それなりの費用を要します。そして➁テレワーク等は、製造業や運送業、建設業など、現場仕事の多い事業所では導入が難しいものです。誰もが使える制度の導入が求められています。
①始業時刻等の変更も、所定労働時間は変更しないので、始業時刻を遅らせた分、終業時刻も遅くなるので、安全管理体制の面から導入が難しいと判断する事業所もあります。誰かの柔軟な働き方が、誰かの負担となる働き方となるのは、制度の趣旨に反すると言えるのではないでしょうか。
となると消去法で➃養育両立支援休暇、⑤短時間勤務制度となってしまうのでしょうか…どちらも無給でも差し支えないとされているので、果たして労働者は実際に利用したいと思えるでしょうか。①~⑤以外の候補を選択できる要素を残して欲しかったものです。
就業規則は事業所ごとに定めるものなので、同じ会社でも本社と工場では別の制度を選択することも可能です。10月までもう少し期間がありますが、意見聴取の機会を設ける観点からすると、意外と時間はないかもしれませんね。
育児が制度化しうまく機能するようになれば、介護との両立についても本格化することでしょう。どんな働き方がわが社には向いているのか、当社は少人数企業なので、月一会議などの機会を使って、全員での意見交換をしたいと考えています。「自分が考える柔軟な働き方とは?」、当社はどの措置を導入することになるのでしょうか…