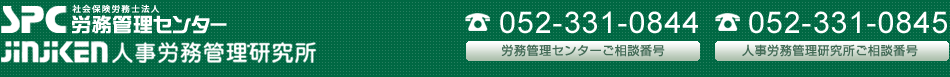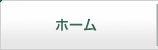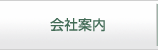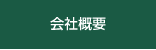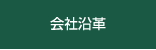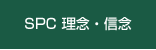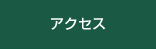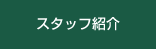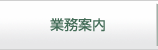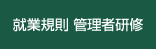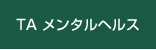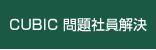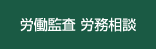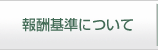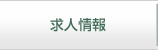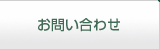勤怠研修からの学び
先日、お客様のところで勤怠に係る研修を部署長、サブクラスを対象に実施させていただきました。
総務人事の担当者も複数回、全役職者向けに実施してきましたが、浸透の効果が上がらずに依頼に至りました。
まず提案したのが目標値をクリアしている部署長、サブを選任いただき、勤怠課題に対する取り組みを30分話していただく。
その後、3つの課題(時間外休日労働の協定における特別条項超越・年次有給休暇取得率・早出残業率)ごとにチームを編成(5人程度)してもらい
次の点を話し合い、結果を模造紙に書き出していただく。所要時間は1時間とする。
1. チームの課題は何か
2. 取り組み事例からのヒントは
3. 課題とヒントのギャップは何か
4. ギャップを埋めるため何をするか
この発表を取締役2名にも聞いてもらい、チームごとに他のチームに対する感想を出し合い、取り組み事例発表の部署長、サブに意見を述べてもらい、2名の取締役に総括していただく。
結果、見えてきたものは2つあります。
ひとつは、「部署長、サブの勤怠管理チェックの細目さ」
そしてもうひとつは、「部下は上司の管理姿勢行動を見ている」ということでした。
取締役が総括された言葉にも大きな学びがありました。
それは、「ここにいる方達は数字には強い。だからこの立場に居る。これからは人に対しても同様の強さがいる。関心がいる。」
そして、「この機会を通して、発信者になっていただかないと浸透はない」という点です。
わたしとスタッフ一名は、場の設定、道具の用意をしただけです。後は主役である部署長、サブの話し合いに耳をそばだて続けました。
各社から同じようなご依頼があります。その時に確信をもって申し上げれることがあります。
「あるべき論を強要する前に、個々人が置かれた状況を観察し、何に困り、何に迷い、何ができるかを、一緒に見つけ出す」
そんな取り組みをご提言することです。