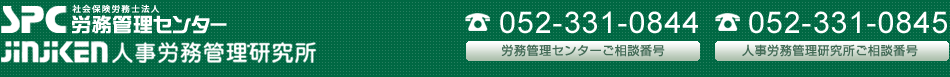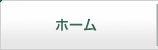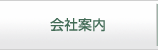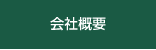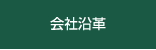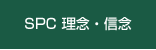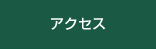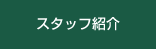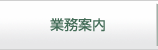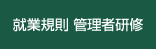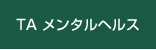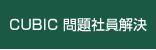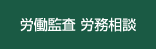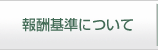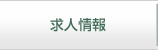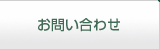アジア共生研究会(バングラデシュ)
9月6日(土)から10日(水)で15名の中小企業家仲間(アジア共生研究会)とバングラデシュに行ってきました。その体験をご紹介したいと思います。
まずは、バングラデシュの位置ですが、南アジアでインドの東端とミャンマーの間にあり、ベンガル湾に面した国です。中部セントレア空港から香港経由で6時間かかります。母国語はベンガル語です。
国の成り立ちは、1947年のイギリスからのインド・パキスタン分離独立の際、「東パキスタン」となりました。そして1971年のパキスタンからの独立戦争で分離、インドの支援を受けて独立しました。
日本は1972年にいち早くバングラデシュを国家として承認しました。このことが「親日」の大きな要因となっています。インドは約80%がヒンドゥー教徒ですが、バングラデシュはイスラム教徒が約90%です。
現地ガイドさん曰く「バングラデシュ人はインド人が大嫌い」とのことでした。支援を受けて独立したのに不思議な気がしますが、「独立の恩」が「搾取されている不信」に変化していったみたいです。
面積は日本の北海道の2倍で人口は1億8千万人(世界第8位)です。平均年齢は29歳です。首都ダッカには4000万人(主にイスラム国への出稼ぎ者が2000万人いるので実質は2000万人)が居ますのでダッカ空港は毎日、出稼ぎ者の帰国と見送りでごった返しています。
ダッカ空港に着いた時も、帰る時も深夜でしたがすごい車と空港内に立ち入り禁止となっている見送り者で大混雑でした。フライト3時間前に空港着の意味がよくわかりました。郷里送金が国の経済を支えているのがよくわかります。
7日は11時にJETROダッカを訪問しました。バングラデシュでは金・土曜日が休みで日曜は平日です。所長の片岡氏(船井総合研究所出身)からポイント5点を教わりました。
1. 大変な親日国。日本政府・JICAの82事務所の中で一番の投資先はインド、二番がバングラデシュということもあり、日本の技術や製品に対する憧れが高い。
2. 日本はなぜそれほどバングラデシュに投資をするのか。それは、ASEANと南西アジアの結節点で、ベンガル湾の要衝としてインド太平洋戦略でも重要な国であるため。
3. 1人当たりのGDP(国内総生産)は2,774USドル。南アジアで最貧はネパールの1,486USドル。ちなみに日本は32,476USドルです。
4. 進出日系企業は330社、ダッカ日本商工会会員企業は150社(2025年8月末時点)。2023年12月から月額最低賃金が上昇(8,000タカから12,500タカへ引き上げ。日本円では9,600円から15,000円)。一般製造工で月額25,000円から30,000円。
5. 学生主体の現暫定政権下で2026年2月に総選挙実施予定。中国寄りの政権が誕生する可能性が高いとのこと。2025年9月だから来れた。これ以降だと町がさらに大混雑して入国困難。
14時30分からはJICAの天田氏の話を聞きました。JETROの復習にもなりましたが、大卒レベルでは英語が日常的でベンガル語は友人・家族内だけで使用するとのこと。この次の訪問先であるご紹介の日本語学校「志(こころざし)」でそのことを実体験しました。
15時30分「志」に着きました。この学校は2022年9月から2025年9月までで約300名の学生が日本語を学んでいます。学長の岡林氏は関西大学出身で15年間学校経営をされています。スキンヘッドの愛嬌のある方です。その岡林氏の「日本語を教えると同時に自分の足で立てるような人材育成」というお話のあと、実際に高度人材として日本の会社に就職が決まっている8名の男女学生と対面させていただきました。お互いを日本語で自己紹介し合い、「好きな日本語」「行きたい都市」等簡単な質問をさせていただきました。その中で一人の男子生徒が好きな日本語は「好き」ですと答えてくれたのが印象に残っています。我々の仕事の内容を理解するときには岡林氏が英語で話したほうが通じました。学生達の英語力の高さを認識しました。
7日最後は日本人経営のラーメン店爛々亭に行きました。社長の吉田氏もこの日ために日本から来てくれてました。スペインのマドリード、日本でも名古屋の中川区、東区、天白区で家系ラーメン店を経営されています。日本から輸入した食材とダッカ製のビール「Hunter」、各自が持ち込んだ日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキーで酒盛りが始まりました。「志」の岡林氏も参加いただけて大変有意義な時間を過ごし明日からの英気を養うことができました。
8日はダッカ郊外にあるアパレル工場とバングラデシュ独立戦争で殉死した知識人虐殺記念碑観光と別れて行動しました。私は、後者に行きましたが、追悼碑にこう記されていました。
「灰の中に消え去ったが、彼らの人生の光は残る」。
その後合流し、ダッカに戻り国立博物館を見学し、次に「ビート・モカッラム国立モスク」を見学しました。このイスラム教モスクは、収容人数が約3万人と国内最大級で金曜礼拝が最も重要とのことでした。当日は月曜日でしたので、人もまばらで、日に6回ある礼拝のはざまでしたので体を横たえて「頭が北、足が南」という姿勢で寝ている方が多くみられました。これは宗教的敬意によるとのことでした。
その後東洋のオックスフォードと呼ばれるダッカ大学に行きました。学生気分でおじさん15名が校内を歩きながら、バイクにのる男子学生に話しかけたりしました。英語でなんとか意思疎通をしましたが、興味深く対応してくれました。残念ながら女子学生には話しかけることができませんでした。シャイなおじさん達です。
9日はグラミン銀行プログラムを体験しました。ダッカ市内にある銀行をイメージしていましたが、ダッカから往復3時間を要して郊外にある村での実際の返済風景を見せていただきました。
グラミン銀行は、経済学者であるムハマド・ユヌス教授が創始者で、2006年には教授と銀行がノーベル平和賞を受賞しています。融資対象は、貧困層、とくに農村部の貧しい女性です。担保なしで少額の融資を行い、自立と生活改善を支援することを目的としています。5人のグループ単位で融資を受け、互いに返済を助け合う仕組みです。なぜ女性なのか、銀行スタッフに質問したところ、女性は家計や子供の教育に資金を回すので、貧困削減効果が高いとのことでした。ただ実際は夫のためにバイクを買ったり、事業資金に使うケースもあり、返済信用度が高いのが女性だからが本質的理由のようです。融資金額は5000タカからスタートして最高でも800万タカ、日本円で6000円から960万円。返済は毎週火曜日、利子はおおむね年利平均10%とのことでした。
このグラミン銀行プログラムの中で感動した出来事をご紹介します。
その1は、バスでは行けない村の中を圧縮天然ガスを燃料とする三輪タクシー5台に15人が分乗して、時速40~50㎞で疾走したことです。まさに平地のジェットコースターに乗っているみたいで、腕や足を車内にちゃんとしまっておかないと狭い路地では超危険でした。皆奇声を上げていました。
その2は、やっとのおもい(時間にすれば10分程度)で屋外にある集会場に着きました。なんとそこには、6組各5人の30名とそれを束ねる総合リーダー1名がサリーと呼ばれる色華やかな伝統服で我々を待っていてくれました。年齢は多分20代から60代と幅があります。彼女たちの前には15名分の椅子が並べられ、そこに座わると代表が何か話をしてほしいとなりました。僭越ながら私が次のような挨拶をさせていただきました。
「我々15名は日本から来ました。バングラデシュは全員初めてです。一番驚いたのは、バングラデシュの皆さんが日本人に対して非常に親しみを感じてくれていたことです。皆さんにお会いできてとてもうれしいです。できれば全員で写真を撮りたいと思いますのでよろしくお願いします。」
すると、通訳していただいた後で、「私たちも会えてうれしい。写真をとるなら化粧をしてくるのに」と返答がありました。すかさず私は「十分にビューティフル」と叫んでいました。その後、返済ノートを使用しての返済が始まりました。それを見届けてから全員で記念写真を撮りました。暑い中で汗が噴き出ましたが50名近い笑顔で映ることができました。
その3は、バスに乗り換え、ちがう地区の統括センターの様なところに行きました。そこも地味な建物でしたが15名分のくだもの・お菓子(レクサスクラッカー)と水が準備されていました。センター長がバングラデシュでは36年前は平均寿命は37歳だったが、現在は67~70歳まで伸びた。これもグラミン銀行の活動が起因していると話されたことが印象に残りました。わたしは折角でしたので、用意されたくだもの・お菓子を全部平らげ、「とてもおいしい。ありがとうございます。」と通訳してもらうと、もっと食べろとくだもののおかわりが出てきました。仲間からは白い目でみられました。
その後ダッカ市内のショッピングモールに行きました。バングラデシュで有名な品を食品売り場の女性に尋ねたところ、紅茶とはちみつとマンゴのゼリーとのことでした。それにグラミン銀行のセンターで出していただいたレクサスクラッカーを購入し、最後に妻と長男の嫁を含めた娘3名に同じバングラデシュ産のバックを4つ購入しました。自分にはモスクで着用する男性用のパンジャビと呼ばれる長袖の膝丈くらいまである上衣を購入しました。人前ではまた1回も着てませんが。
10日深夜にダッカ空港へ行きましたが、冒頭で紹介したように凄い車の渋滞、人の数でした。我々の目の前で、母親が他国に行く息子(20代ぐらい)の頬に何度も泣きながらキスをしている姿が感動的でした。どこの国でも子供にむける愛情の深さは一緒なんだなと感じ入りました。
当初はいままでアジア共生研究会で行ったことのないバングラデシュかネパールどちらに行くかと議論し、9月ではエベレストは雲にかかって見えないからバングラデシュと、残り物的な好奇心からの選択でした。それが実際に行ってみて、台湾以上の親日感に感動すら覚えました。ぜひ数年後にもう一度訪れてみたいと強く思います。今後もこの国に関心を向けて、胸を張って行けれる日本人であることを目指して精進したいと思います。