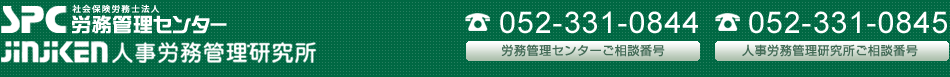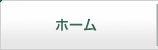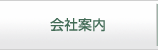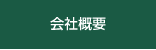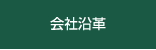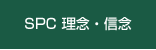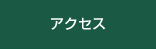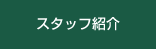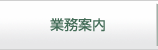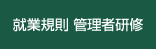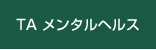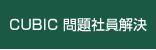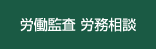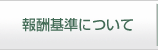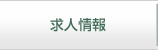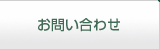在職老齢年金の見直し
近年、人手不足や技能継承等の理由で、働く高齢者の割合は増加しています。
総務省の労働力調査によると65歳~69歳の就業率は、2003年に34.7%だったのに対して、2023年は53.5%に増加しています。
一方で65歳になると多くの方が年金を受給するようになりますが、一定額以上の給与(報酬)が出ている場合、年金額を調整する仕組みがあります。これを「在職老齢年金制度」と言います。
現在の基準では、給与と厚生年金の合計額がひと月51万円を超えると、超えた部分の半分の年金が支給停止となります。
(例)
ひと月の給与が45万円、厚生年金がひと月10万円の場合、合わせて55万円となります。
この55万円に支給停止基準額である51万円を引くと、4万円となります。4万円を半分にした2万円が支給停止となります。
結果として、厚生年金の支給額は、10万円-2万円された8万円となります。
*上記の「給与」には賞与を12分の1したものも含まれています。
この在職老齢年金の仕組みにより、働く年金受給者の約16%が支給停止されています。
同時に、年金が支給停止にならないように、働く時間を調整するケースも見受けられます。いわゆる、働き控えに繋がっているとも指摘されています。
人材不足で働いてもらいたい企業側と働きたくても働けない労働者側の双方にとってデメリットが生じている現状があります。
このため、厚生年金が支給停止となる基準額を月51万円から62万へ引き上げることが予定されています。
先程の例の場合では、基準額が引き上げられると調整されていた2万円も支給される形になります。
基準額が引き上げられたことにより、調整されていた年金が過去に遡って支給されることはありませんので、ご注意ください。
また、現在の法律では、停止される年金は厚生年金の部分のみになりますので、国民年金の部分等は給与が多いことにより調整される仕組みはありませんので、ご安心ください。
今後も健康寿命の改善や人手不足の影響もあり、高齢者を雇用する企業の割合は増加することが見込まれます。それに伴って、転倒などの高齢者の労災も増加傾向にありますので、労働災害防止の重要性も高まっていくかと思います。