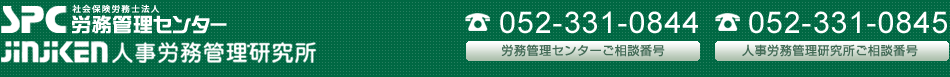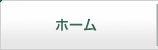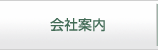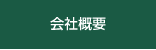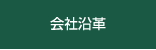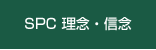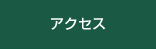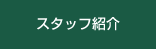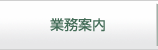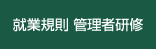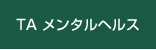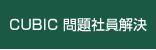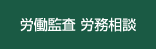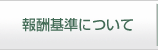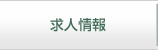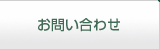給与明細の見方について
2025/04/18
新入社員の皆さん、ご入社おめでとうございます。今年は桜の持ちがよく、綺麗な桜と一緒に写真を撮った方も多いのではないでしょうか。
会社によって給与の締め日は違いますが、10日締めや15日締めの会社に入社した方は、今月、初任給を受け取るという人もいると思います。当然ながら、4月1日から数えて、10日締めの会社なら10日間、15日締めの会社なら15日間の在籍期間しかありませんので、基本給などの月で決まった給与は、日割り計算されるため、雇用契約書の金額とは異なります。
「初任給で親へプレゼント」は今でも定番のようですが、私が新卒入社したときを振り返ると、初任給のあまりの少なさに「とてもじゃないけど買えない!!」と愕然としたものです。欠勤することなく働けば、5月の給与でちゃんと雇用契約書通りの金額が支払われるので、安心してください。
最近は、新入社員に向けた研修の中で、給与明細の見方を取り上げるところも増えたと耳にします。雇用契約書の記載金額は、支給される金額なので、そこから何がどれだけ控除されるかを知っておくことはとても大切です。もちろん控除についても雇用契約書に記載はありますよ。
まずは雇用保険料。週20時間以上の就労をする人は、どんな会社に勤めていても、雇用保険に加入します。事業の種類により料率は分かれますが、一般の事業であれば、現在の労働者負担分の保険料率は「0.55%」です。22万円の支給であれば、雇用保険は「1,210円」控除されます。
次に、健康保険料。保険者が協会けんぽ愛知支部であれば、現在の保険料率は「10.03%」です。健康保険料は会社が半分負担してくれますので、22万円の支給であれば、健康保険料は「11,033円」控除されます。
そして、厚生年金保険料。現在の保険料率は「18.30%」です。健康保険料同様に会社が半分負担してくれますので、22万円の支給であれば、厚生年金保険料は「20,130円」控除されます。
健康保険と厚生年金保険は、会社規模や、法人か個人経営かで加入要件が変わりますが、一般的には週30時間以上の就労をする人が加入します。雇用保険料の計算と違い、「等級」と呼ばれる枠組みがあるため、支給額に料率を掛けて計算するものではありません。
250129_kenpo_保険料率_graphic_leaflet_aichi_no_trm_H4
控除されるもの、まだ続きます。所得税が毎月、源泉徴収されます。扶養する人がいなければ、今年の税額表でみると「4,340円」控除されます。
22万円から、4つの控除項目を引くと「183,287円」になりました。
あとは、親睦会費や寮費など、あらかじめ給与から天引きすることを、会社と労働者とで約束している会社に入社した人は、その費用も控除されます。
健康保険料と厚生年金保険料は、多くの会社が「翌月徴収」の仕組みを取っているので、4月支給の明細には載っていなければ、5月から控除が始まります。
月の給与だけでなく、賞与が出る会社なら、賞与からもこの4つの控除項目が控除されます。賞与額が多ければ、その分控除される額も多いです。計算方法を知っておけば、賞与の使い道の計画も、楽しく立てることができますね。
12月には年末調整と言って、1年間の所得に対する税金の総計算が行われます。税金は自分が国税庁に申告すべきものですが、会社が代わりに手続きを取ってくれるのが「年末調整」です。10月下旬から11月に、会社から年末調整の案内があった際には、面倒と思ってはいけません。期限までにちゃんと報告しましょう。
期限が守れない人は、年が明けて「確定申告」をすることになります。最近はマイナポータルとの連携で、ずいぶんと「確定申告」も楽になっているので、仕組みを理解するためにはお勧めですが、事前に会社に「確定申告」することは伝えましょう。
さあ、入社2年目を迎えました。6月支給からは新たな控除項目「住民税」が増えています。前年の所得がある人が、住民税の納付義務を負うため、入社1年目にはなかった税金の控除が始まるのです。住民税も「特別徴収」することで、会社が代わりに納付をしてくれるものです。会社を辞めると「普通徴収」に切り替わり、こちらは年4回と決まっているので、3ヶ月分の住民税をまとめて納付する必要があります。「特別徴収」は有難いですね。
5つの控除項目それぞれが、どんな制度なのかまでは今回は触れませんが、ChatGPTやMicrosoft CopilotなどのAIにぜひ聞いてみてください。
今回は控除項目を取り上げましたが、給与明細には、勤怠項目と支給項目もあります。給与明細は、見方が分かると、案外面白いものです。