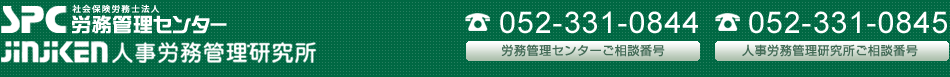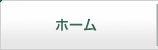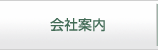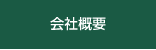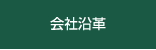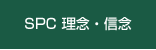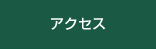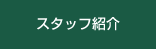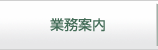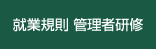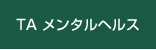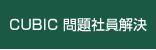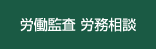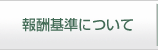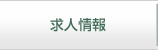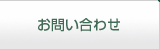被扶養者の認定基準について
健康保険法の被扶養者についてお伝えします。
被扶養者になれる要件は、主として被保険者によって生計を維持されていることですが、続柄や被扶養者の収入等によって判断されます。
1・続柄の要件
国内に居住する
①直系尊属・配偶者(事実上を含む)・子・孫・兄弟姉妹
②①以外の3親等内の親族
③事実婚の配偶者の父母及び子
④③の配偶者の死亡後のその父母及び子
が対象となります。
①の場合は被保険者と同居していなくても対象となりますが、②③④の場合は被保険者と同居していることが要件となります。
なお、国内居住が原則ですが、外国での留学生など国外居住であっても被扶養者となる特例もあります。
2・被扶養者の収入の要件
原則、被扶養者の年間収入が130万円未満であることです。(60歳以上または一定の障害状態にある人は180万円未満)
さらに、被保険者と被扶養者が同居している場合には、被扶養者の収入が被保険者の収入の1/2未満であること。別居している場合には、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが要件になります。
このように、原則は、年収が130万円未満であれば、被扶養者に認定することができますが、昨年施行された「社会保険の適用拡大」の要件に該当する場合は、被扶養者の対象外となる場合があります。要件の①51人以上の企業に勤務していること②月88,000円以上の収入があること③週20時間以上働いていること④2か月を超えて雇用されていること⑤学生でないこと これらの要件すべてに該当するのであれば、自らが社会保険に加入しなければならないため、たとえ130万未満であっても被扶養者にはなれません。
また、年収に含まれるのは、給与だけではないので注意が必要です。退職した場合の雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金等も含まれます。
失業給付については、年収が失業給付のみの場合、基本手当が、3,612円以上となった場合に、扶養から外れることになります。
その他、よくあるご質問としては、夫婦共働きの場合、子供はどちらの扶養に入ればいいのかということですが、原則として、年収の多いほうの被扶養者になります。その場合の年収は過去の収入、現時点の収入、将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額で判断することになります。なお、夫婦の年収の差額が1割以内である場合は、届出による方の被扶養者となります。