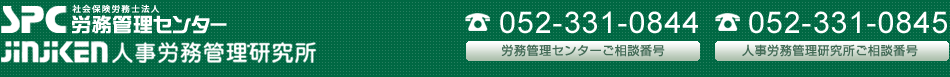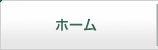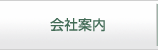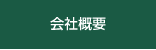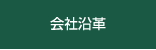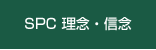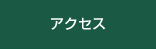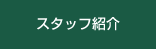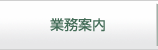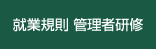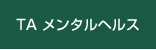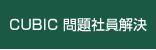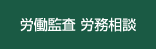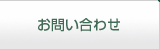■私傷病休職者の職場配置(労務受領拒否)
2016/02/21
今回のスタイルは、
1.テーマにそった最高裁判所判決の重要判例紹介
2.1.に関連する昨今の労働判例紹介
3.1.と2.について私的見解を展開
で進めていきます。
まず、労働契約における民法上の条文を確認しておきたいと思います。
民法623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」。
民法543条「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」。
民法624条1項「労働者は、約束した労働を終わった後でなければ、賃金を請求することができないのが原則である」。しかし、民法493条「実際の労務の提供がない場合であっても、労働者が労働契約に従った労務の提供をしていると判断されれば」、民法536条2項「使用者が不当に労働者の就労を拒否している場合には、労働者は賃金請求権を失わない」。
それでは、第1回目をはじめたいと思います。
取り上げる最高裁判例は、次のものです。
私傷病休職者の職場配置(労務受領拒否)~片山組事件(最高裁平成10年4月9日判決)
片山組事件-「私傷病休職者の職場配置(労務受領拒否)」
Xは、Y(従業員約130人の土木建築会社)に昭和45年に雇用された。Xは、平成2年夏にバセドウ病と診断され治療継続するもYに告げず平成3年2月まで現場監督業務を継続した。Xは、平成3年8月19日に、Yから翌日からの現場監督業務の命令を受けた際、バセドウ病のため現場作業ができないこと、残業は1時間に限り可能であり、日曜と休日の勤務は不可能である旨を申し出た。
Yは、Xに対し、診断書と病状補足説明書面の提出を求め、その結果現場監督業務に従事することが、不可能と判断し、平成3年10月1日より自宅療養を命令した。その後Xは、同命令に対して、事務作業を行うことはできるとして、主治医作成の診断書を提出したが、YはXが現場作業を行いうることが明らかとなった平成4年2月5日まで自宅治療命令を持続した。Yは、Xの自宅療養期間中は欠勤とし、賃金不支給および平成3年冬期賞与は減額支給したが、Xは、賃金と一時金減額分の支払を求めて提訴した。
1審(東京地裁平成5年9月21日判決)は、Xの賃金請求権を認めたが、2審(東京高裁平成7年3月16日判決)は認めなかった。Xは上告した。結果、賃金請求権が認められるとして、高裁判決を破棄し、高裁に、配置される現実的可能性があったとどうか審理のやり直しを命じた。なお、差し戻し審では、Xの請求が認容された。
<判決からのメッセージ>
「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務についての労務の提供が十全にできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」「そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。」
→職種・業種が特定されていない従業員について、「一部」就業できなくなったときは、本人が担当している業種でない軽易な業種等で、実際に就業可能な「現実的可能性」があるときは、従業員が労務提供を申し出ている限り、可能な業務をさせることで賃金を保障しなければならない。
<メッセージに対する私的見解>
「職種限定契約」を締結していない限り、私的な健康上の理由であっても、「最も軽易な業務」への配置転換を申し出られたら拒否できない、という判断です。
これは、休職期間満了時の労働契約の終了(自然退職)の場面においても影響してくる内容です。昨今の判例でも取り上げます。
次に昨今の判例ですが、取り上げるのは次の判例です。
休職期間満了時の自動退職扱い~第一興商(本訴)事件(東京地裁平成24年12月25日判決)
第一興商(本訴)事件-「休職期間満了時の自動退職扱い」
Xは、Y会社の正社員として勤務していたところ、上司などから仕事を与えられず、嫌がらせを受けたり暴言を浴びせられるなどしたうえ、精神的に追い込まれて視覚障害を発症し、休職に追い込まれた結果、休職期間満了により自動退職という扱いになった。Xは、①同視覚障害は業務上の傷病に当たり、その療養期間中にXを自動退職とすることは労基法19条1項(解雇制限)により無効である。②休職期間満了時点で復職可能な状況にあった、としてY会社に対して、雇用契約上の地位確認、自動退職後の賃金の支払、そして安全配慮義務違反、不法行為があると主張して損害賠償を請求した。
結果、東京地裁は、発症と業務の関係を否定する一方、主治医の復職可能との意見に対し会社は配属先がないなどの反証をせず、休職事由は消滅していたと判示。事務職での通常業務は可能で退職無効とした。
<判決からのメッセージ>
「Y会社は、Xに産業医の診察を受けさせたり、Xの復職の可否について産業医の意見を求めた形跡すらないものであって、復職不可としたY会社の判断こそ客観性を欠く」
→使用者が労働者を配置できる現実的可能性がある業務が存在しないことについて反証を挙げない限り、休職事由の消滅が推認される。
<メッセージに対する私的見解>
職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した労働者については、復職の可否を判断する際に、休職前に従事していた職務だけでなく、その労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることが出来るか否かも検討しなければならない、まさに、片山組事件最高裁判決の影響を受けています。そうなると、法的に義務のない休職期間を設けて、当該期間が満了したにもかかわらず、普通解雇や自然退職は難しいということになるのでしょうか。
中小零細企業においては、①従業員の能力が低く、②企業の人的規模が小さく、③配置・異動の実績もなく難易である場合は、信頼できる医師の診断を参考にしながら、休職規定にもとづく自然退職は可能でなければいけないと考えます。
最後に、片山組事件と第一興商(本訴)事件、両方を見据えながらいえることですが、私傷病後の職場復帰に当って、その健康状態に配慮して勤務を軽減した場合における賃金については、職務内容の変更による賃金規程にもとづく減額はやむを得ないと考えます。特に、今日では増え続けるメンタルヘルス不全者に対する復職問題は大きな課題となります。精神障害には「治癒(ちゆ)」という概念がなく、「寛解(かんかい)」という概念に止まる以上、復職に当って軽減勤務・リハビリ勤務の際の賃金取り決めは健常者に対する職場環境の視点からポイントとなってきます。
会社の信頼する産業医が、復職可能という判断をした場合は、復職を検討することが一般的となります。その際、いきなり短時間勤務では、健常に働く従業員に対する物理的・精神的両面で職場環境が悪化します。そんな時に、「賃金支払無しのお試し勤務」を本人と会社で書面に交わし期間も決めて実施する方法をおすすめします。通勤時も勤務時も労災保険は使えないこととか、義務ではないので何時来ても何時帰っても構わないと等の取り決めをしっかり締結することが必要になります。その後、時間給による短時間勤務を実施すれば、健常者に対する職場環境配慮になると考えます。
以上です。