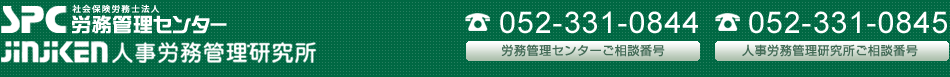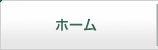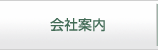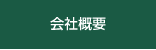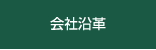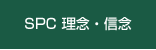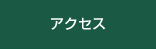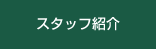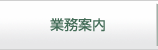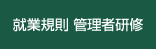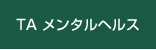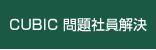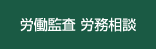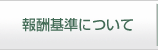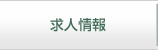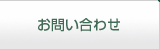カスハラ・就活セクハラ防止措置が義務化
近年、顧客からの過剰な要求や暴言による「カスタマーハラスメント(カスハラ)」、そして採用活動中の「就活セクハラ」が社会問題化しています。こうした行為は従業員や求職者の心身に深刻な影響を与え、企業の信頼を損なう原因にもなります。「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が交付(2025年6月11日)され、2026年10月1日に施行予定である改正内容(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法が一部改正)では、防止措置の義務化が明確に定められることとなりました。
〇カスハラとは?
以下の3つの要素をすべて満たすものです。
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境を害する行為
こうした行為は従業員のメンタル不調や離職につながり、企業にとっても大きなリスクです。
◇事例
ある小売店では、返品対応をめぐって顧客が長時間の電話で暴言を繰り返し、担当者が強いストレスで休職。企業は対応マニュアルを整備していなかったため、現場任せになり、結果的に人材流出につながってしまった。
◇考えられる企業の具体的措置
- 事業主の方針等(消費者の不当な要求は拒否する等)を明確に策定し、社内外に周知・啓発する
- 相談体制を整備し周知する
- 発生時には迅速かつ適切な対応(事実確認や被害者支援)、防止措置を行う
- 相談者への不利益取り扱いを禁止する
〇就活セクハラとは?
採用活動中に、面接官や社員が求職者(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対して不適切な言動をすることです。例えば、プライベートな質問、身体への接触、内定をちらつかせた不当な要求などが該当します。
◇事例
ある学生は、面接後の懇親会で面接官から「恋人はいるの?」と質問され、さらに個人的な連絡先交換を強要された。学生はSNSで体験を投稿し、企業の採用ブランドは大きく傷ついてしまった。
◇考えられる企業の具体的措置
- 事業主の方針等(求職者へのセクハラを許さない、面談等を行う際のルール等)を明確に策定し、社内外に周知・啓発する
- 相談体制を整備し周知する
- 発生時には迅速かつ適切な対応(事実確認や被害者への謝罪等)、防止措置を行う
- 面接官や採用担当者への研修を実施
- 相談者への不利益取り扱いの禁止をする
この義務化は、企業にとって「信頼を高めるチャンス」と言えます。早めの準備で従業員と求職者の安心を守り、企業のブランド価値を向上させましょう。