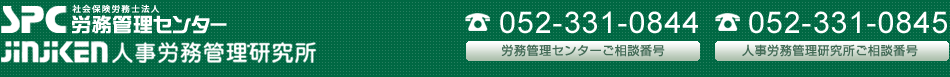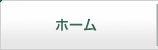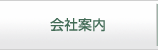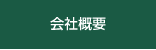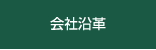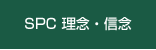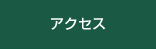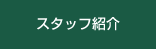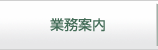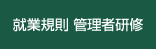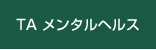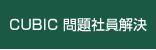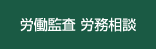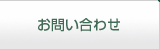「振休」と「代休」の違い
今日は、「振休」と「代休」の違いについて書きたいと思います。
「振休」と「代休」は似て非なるもの
会社勤め方であれば往々にして「代休」又は「振替休日」を取得することが考えられますが、両者は似て非なるものです。ただ、両者を混同して運用しているケースも少なくありません。たとえば、日曜日に急な仕事が発生したため出勤し、次の火曜日に休みを取ることにしたら、これは「振替休日」と「代休」どちらになると思いますか。
そもそも「休日」とは、労働契約において、労働義務がない日をいいます。労働基準法上では、毎週少なくとも1回の休日(または4週を通じ4日以上の休日)を与えなければならないとされており、これを「法定休日」といいます。週休2日制の企業の場合は、休みが2日あるわけですが、「法定休日」とそれ以外の「所定休日」があることになります。行政通達では、法定休日の曜日を特定することが望ましいとされており、義務とはなっていないものの、法定休日を「日曜日」など、特定の曜日に決めている企業もあるでしょう。一見すると、どちらも同じ休日です。違いがあるとすれば、割増賃金の考え方です。
法定休日に働いた場合は、3割5分以上の割増賃金が支払われることになりますが、所定休日に働いた場合は、残業と同じ取り扱いとなって、法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えた時間について2割5分以上の割増賃金が支払われることになります。こうした基礎知識を押さえたうえで、振替休日と代休の違いを見ていきましょう。振替休日とは、就業規則等にあらかじめ休日と定められた日を、事前に労働日と交換することをいいます。
たとえば、会社の休日である日曜日を、同じ週の水曜日と交換するようなケースを想像していただけるとわかりやすいでしょう。休日を繰り下げるだけでなく、前の週の木曜日に繰り上げて振り替えることも可能です。1週間の起算日は、特に定めていない場合に日曜日となります。これにより、あらかじめ休日と定められた日が労働日となり、その代わりとして振り替えられた日が休日となります。つまり、所定休日はもちろん、法定休日であっても、振り替えたことにより休日労働にはならないので、同じ週に振り替えて週の法定労働時間を超えていないかぎり、割増賃金は発生しません。
ただ、週をまたいで休日を振り替えるときは、1週間の法定労働時間を超えた場合に割増賃金が必要となり、実際は割増賃金が発生するケースが少なくありません。それにもかかわらず、支払われないことがままあります。この点は誤解が多いところなので、気をつけたいところです。振替休日を利用するには、まず就業規則等で休日の振り替えが規定されていること、そしてあらかじめ休日と振り替える日を具体的に特定しておく必要があります。ここでいう「あらかじめ」とは、少なくとも前日の勤務終了時刻までを指します。さらに休日を振り替える場合においても、4週間を通じて4日以上の休日が与えられなければなりません。
代休=休日出勤の代償として休むことなのか
振替休日は、事前に振り替える日を特定するのに対して、代休は事前にこうした措置を行うことなく、実際に休日に働いてしまってから、代償として他の労働日を休日として休むことをいいます。 たとえば、休日である日曜日に急な仕事で出勤し、その代償としての水曜日に休むような場合などです。こうしたケースは、意外と多いのではないでしょうか。代休の場合は、いくら後で休みを取っても、休日労働という事実が先行するため、法定休日に働いてしまった場合は35%以上の割増賃金が必要となります。
ところで、この代休は、従業員側から当然に請求することができるのでしょうか。休日出勤する立場からすれば、休みの日に会社の都合で働いているのだから、その代償として自分が休みたい日に休めるものだと思われるかもしれません。しかし、代休制度は法律上において使用者に義務が課されているものではないのです。つまり、就業規則等の定めによって、初めて代休の付与を求める権利が生じます。 そこで、注意したいのは、あなたの会社のワークルールがどのようになっているかということを確認しなければなりません。代休と振替休日の両方を定めている場合もあれば、振替休日のみの場合もあります。
振休取得を推奨する会社も増えている
昨今は働き方改革を推進する流れもあり、休日出勤や残業をどう削減するかが各企業の課題といえます。そうした中で、休日出勤を事前申請により労働日と振り替える対応を推奨しているケースが増えているように感じます。休日に働かなくて済むのなら、それが1番です。しかしながら、働かざるをえない場合もあるかもしれません。「振休」と「代休」は特に誤解の多いところといえます。気持ちよく働くためにも、労使双方において正しい認識を持つことが大切ではないでしょうか。